日本男児の青春の思い出、ブルマーは絶滅した。
それには「人の嫌がることはしない」原理主義とでもいえる
イデオロギーが関わっていた。人の顔色を窺い、
ビクビク萎縮した今の日本が、理想の社会なのか?
過剰なセクハラ規制・禁煙運動に負けず、ささやかな愉しみを享受する
ために、現役精神科医がおくる知的"闘争"参考書!
表紙にブルマーの誕生から消滅までの写真入年表付。
(Amazonより)
私の評価:





もっと読む»
~評論~
まず、話の対象としなければならない。と言うか避けては通れない印象の残る本書のタイトルですが、これはブルマーWという単語にグッとくる方には惹かれるでしょうし、気持ち悪いと思われる方には退かれるでしょう。ちなみに私は前者でした。(ブルマーフェチというわけではありませんが) これは例えば以前、「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?
 」という本が話題になりましたが、この本の場合は多くの方が読みたくなるような印象づけたタイトルだったのではないかと思います。しかし、本書の場合、印象づける1つの賭けだったように思えます。ブルマー好きを惹きつけ、女性層を捨てるとも取れる賭け。しかし、私は本書を読み終えてタイトルはこれで正解であったと思いました。(商業的にどうなのかは別として)
」という本が話題になりましたが、この本の場合は多くの方が読みたくなるような印象づけたタイトルだったのではないかと思います。しかし、本書の場合、印象づける1つの賭けだったように思えます。ブルマー好きを惹きつけ、女性層を捨てるとも取れる賭け。しかし、私は本書を読み終えてタイトルはこれで正解であったと思いました。(商業的にどうなのかは別として)
ですが、私もなるべく誤解を減らすために書いておきたいと思います。本書はブルマーフェチの精神科医が1冊丸々ブルマーについて語りつくす本ではなく、あくまで話の切り口としてブルマーを取り上げたものである。しかし、著者のブルマーへの執着(愛)は相当なものである。ということです。
それにつきましては、Amazonの方で最初の数ページ(目次や序章)でただで読むことが出来ますので、そちらから読み取ることが出来ます。
まずは序盤のブルマーの部分について話したいと思います。私の世代(1987年生まれ)では小学校中学年あたりまではブルマーを確認できた気がしますが、高学年、遅くとも中学からは女子は皆ハーフパンツになったのではないかと記憶しています。(本書に書いてあるブルマーの歴史と照らし合わせても符合します。) そのため、ブルマーに対する性の意識、著者の言うブルマーへの甘酸っぱさ、青春という恩恵を受けることはありませんでした。ちなみに、こういったあってもなくても社会の根本には影響は無いが、無ければ確実に何かが失われるようなものを本書では「辺緑」と言い、これはこの本の重要なテーマでもあります。
ブルマーを切り口にジェンダーフリーW、医療裁判で問題になることも多いインフォームド・コンセントWなど今、社会で話題に良くあがるような事柄を精神科医という見地から批判していきます。これについては私も本当にうなずくことばかりで、序盤のブルマーに関する話に負けず劣らず面白く飽きることがありませんでした。ただ、一つ言うならば性同一性障害について述べているところで著者がクリスチャンであるためか、聖書を引用して紐解いて行くわけですが、クリスチャンではない私にとっては若干いただけなかったかなと思いました。(それについては後書きで著者も注釈を入れていますが)
ちなみに私は最後の方のこの文章にこの本の全てが凝縮されているように思い、印象的でしたので引用させて頂きます。
この文章だけを見るとなんてひどい、古い悪しき社会だと思われる方もいるかもしれませんが、本書を読みむことで、この文章を読む頃には充分納得のいく文章と思えるようになるのではないでしょうか。私はそう思います。
私は本書を読み、改めて、常識とは何だろう、平等とは本当に善なのだろうかと自分に問いただされました。
追伸:よくよく思い返してみたらブルマーでなくてもハーフパンにはハーフパンの良さがあったなと。それは何かと言うと、体育座りをしている子を見ると、そのハーフパンの中が見えそうで見えない。チラリと見えそうで見えなイズム的、そんなもどかしさも、ある意味一つの良さかもしれません。とは言ってもブルマーの感じるそれには到底及ばないものなのかもしれませんが・・・。
~評論~
まず、話の対象としなければならない。と言うか避けては通れない印象の残る本書のタイトルですが、これはブルマーWという単語にグッとくる方には惹かれるでしょうし、気持ち悪いと思われる方には退かれるでしょう。ちなみに私は前者でした。(ブルマーフェチというわけではありませんが) これは例えば以前、「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?
ですが、私もなるべく誤解を減らすために書いておきたいと思います。本書はブルマーフェチの精神科医が1冊丸々ブルマーについて語りつくす本ではなく、あくまで話の切り口としてブルマーを取り上げたものである。しかし、著者のブルマーへの執着(愛)は相当なものである。ということです。
それにつきましては、Amazonの方で最初の数ページ(目次や序章)でただで読むことが出来ますので、そちらから読み取ることが出来ます。
まずは序盤のブルマーの部分について話したいと思います。私の世代(1987年生まれ)では小学校中学年あたりまではブルマーを確認できた気がしますが、高学年、遅くとも中学からは女子は皆ハーフパンツになったのではないかと記憶しています。(本書に書いてあるブルマーの歴史と照らし合わせても符合します。) そのため、ブルマーに対する性の意識、著者の言うブルマーへの甘酸っぱさ、青春という恩恵を受けることはありませんでした。ちなみに、こういったあってもなくても社会の根本には影響は無いが、無ければ確実に何かが失われるようなものを本書では「辺緑」と言い、これはこの本の重要なテーマでもあります。
ブルマーを切り口にジェンダーフリーW、医療裁判で問題になることも多いインフォームド・コンセントWなど今、社会で話題に良くあがるような事柄を精神科医という見地から批判していきます。これについては私も本当にうなずくことばかりで、序盤のブルマーに関する話に負けず劣らず面白く飽きることがありませんでした。ただ、一つ言うならば性同一性障害について述べているところで著者がクリスチャンであるためか、聖書を引用して紐解いて行くわけですが、クリスチャンではない私にとっては若干いただけなかったかなと思いました。(それについては後書きで著者も注釈を入れていますが)
ちなみに私は最後の方のこの文章にこの本の全てが凝縮されているように思い、印象的でしたので引用させて頂きます。
これは、ユートピアだろうか。そうではない。それどころか、ついこのあいだまで、日本の社会はおおむねこのような社会だった。喫煙者は、好きなところで吸っていた。世の中には、適度のエロスが漂っていて、特別な場所に行かなくても、日常生活の中で程よい性的な満足を感じることができた。廊下に立たされて体罰だと騒ぎ立てたり、先生に叩かれたからといっていきなり告訴するような生徒も親もいなかった。
この文章だけを見るとなんてひどい、古い悪しき社会だと思われる方もいるかもしれませんが、本書を読みむことで、この文章を読む頃には充分納得のいく文章と思えるようになるのではないでしょうか。私はそう思います。
私は本書を読み、改めて、常識とは何だろう、平等とは本当に善なのだろうかと自分に問いただされました。
追伸:よくよく思い返してみたらブルマーでなくてもハーフパンにはハーフパンの良さがあったなと。それは何かと言うと、体育座りをしている子を見ると、そのハーフパンの中が見えそうで見えない。チラリと見えそうで見えなイズム的、そんなもどかしさも、ある意味一つの良さかもしれません。とは言ってもブルマーの感じるそれには到底及ばないものなのかもしれませんが・・・。
ブルマーはなぜ消えたのか―セクハラと心の傷の文化を問う

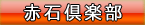
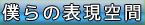
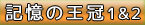








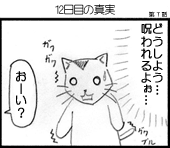





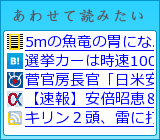

コメント